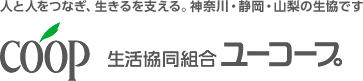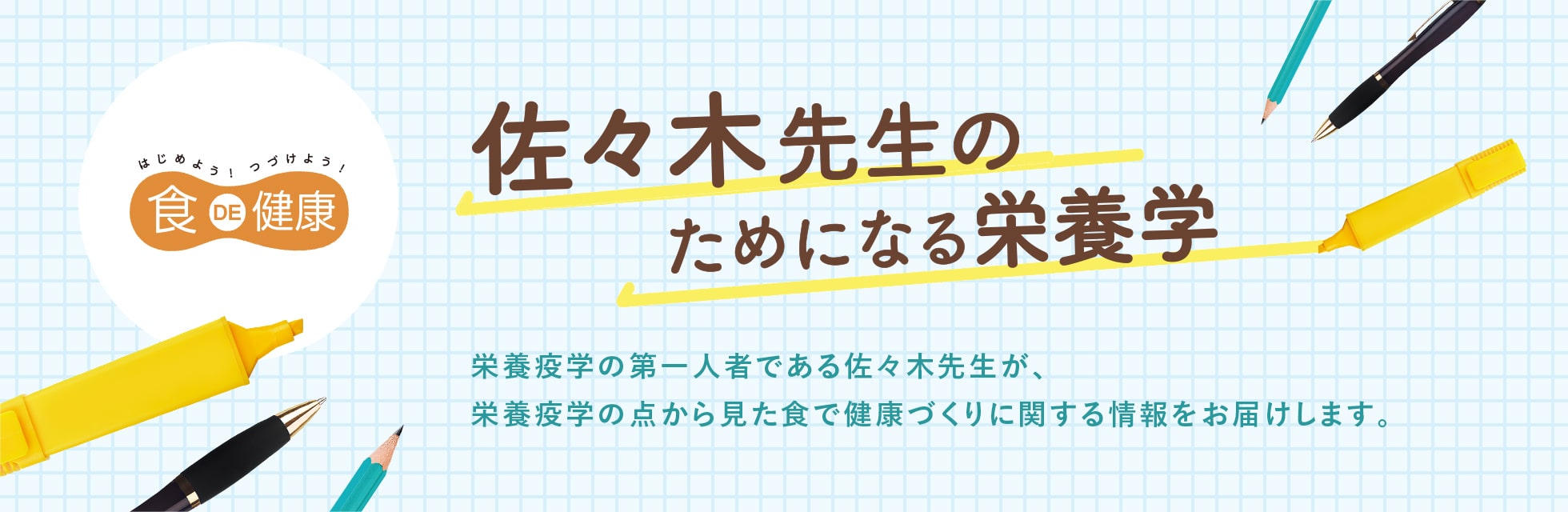
食DE健康テーマ
「鉄」
Q 01生理のときの出血量が多いのですが、鉄欠乏性貧血になりやすいでしょうか?
A 01鉄欠乏性貧血のリスクは、鉄の摂取量よりも生理のときの出血量の影響を強く受けているようです。
鉄欠乏性貧血とは、体内の鉄(赤血球に含まれるヘモグロビンの中の鉄)が不足して起こる貧血です。女性の場合、鉄を失う原因のほとんどは生理のときの出血(月経血)によるものですが、この量を正確にはかることは難しく、鉄欠乏性貧血の研究は乏しいのが現実です。自己申告による経血量と鉄欠乏性貧血の有無の関連をみると、「出血量が少ない(軽い)」と答えた人のリスクは「普通」と答えた人のリスクのわずか3割で、逆に「多い(重い)」と答えた人は2倍近くになりました。出血量が「多い」と答えた人は「少ない」と答えた人の6倍近くも貧血のリスクが高いという結果です(図1)。

あわせて、同じ人たちで鉄の摂取量と鉄欠乏性貧血の有無の関連をみると、鉄の摂取量が多くても少なくても(図2)、また種類がヘム鉄であろうと非ヘム鉄であろうと、貧血のリスクには関連していませんでした。

これらのことから鉄欠乏性貧血は、鉄の摂取量よりも、生理のときの出血量の影響をより強く受けていることが分かります。ご質問のように経血量が多い人、すでに鉄欠乏性貧血にかかっているか、今までにかかった経験がある人は、かかりやすい体質だと考えて、積極的に鉄をとる努力をすべきです。
一方で、経血量が「少ない」か「普通」で、鉄欠乏性貧血の経験がない人は、それほど神経質にならなくてもよいと思います。
鉄はすべての人が気をつけるべき栄養素ではないようです。女性の場合、鉄欠乏性貧血のおもな原因は生理のときの出血です。ご自分の生理の特徴と食品の好みを把握したうえで、賢く鉄をとっていただきたいと思います。
[参考文献]
Asakura K,et al. Iron intake does not significantly correlate with iron deficiency among young Japanese women: a crossesctional study. Pubic Health Nutr 2009;12:1373-83.
詳しくは『佐々木敏の栄養学のすすめ(165~174ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。
機関誌mio 2019年4月号掲載
Q 02レバーが嫌いなのですが、レバー以外で鉄分を多くとるにはどうしたらよいでしょうか?
A 02吸収率まで考慮すると、体の中で有効に使われる鉄は肉や魚に多く含まれています。
鉄欠乏性貧血の予防のための食事によくレバーがすすめられますが、これはなぜでしょうか。私たちが食品から摂取している鉄は、ヘム鉄と非ヘム鉄に分かれます。ヘム鉄とは赤血球のヘモグロビンの中にある鉄で、わずかでも血液が含まれる食品に含まれています。
血のかたまりのようなレバー(肝臓)はヘム鉄を多く含む食品の代表といえますが、肉や魚にもヘム鉄が含まれています。非ヘム鉄はそれ以外の鉄で、通常、鉄そのものの形で、植物性食品にも広く含まれています。
ヘム鉄と非ヘム鉄では腸からの吸収率が異なり、ヘム鉄は約30〜40%が吸収されて体内で使われますが、非ヘム鉄の吸収率は5%程度だと報告されています。これが、レバーが鉄欠乏性貧血予防にすすめられる理由です。とはいえ、レバーだけが大事ではないことはもうお分かりですね。

生理のときの出血量(自己申告による)と鉄欠乏性貧血の有無の関連
仮に、表1の〔A〕のような頻度で7つの食品を食べている場合、鉄の吸収率まで考慮すると、〔E〕の「体で有効に使われる鉄の量」はレバーより肉や魚のほうが多くなります。
普段食べている動物性食品を大切にすれば、レバー以外からでも鉄は摂取することができます。この結果は食べる頻度や量によっても違ってきますので、自分の好みや食生活を生かしながら、上手に鉄をとっていただきたいと思います。
レバーは吸収率の高いヘム鉄の代表ですが、肉や魚も鉄の吸収率が高いので、普段食べている動物性食品の大切さを見直しましょう。
詳しくは『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ(165~174ページ)』(女子栄養大学出版部)をご覧ください。
機関誌mio 2019年5月号掲載